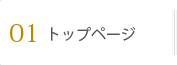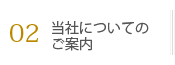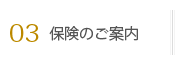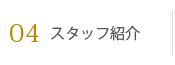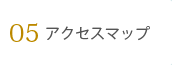カテゴリ:「 スタッフブログ 」のブログ記事一覧
「八十八夜の別れ霜」
2013.03.28 | カテゴリ:スタッフブログ
こんにちは。更新が遅くなってます。
古い話で恐縮ですが、以前に中尾が、このブログにバレンタインデーの記事を載せました。
その中で、バレンタイデーから派生した記念日(?)が数々あり、5月13日は「八十八夜の別れ霜」にちなんだ「別れの日」(メイストーム)とのこと。ちょっと待った。5月13日とはなんと中途半端な。「八十八夜の別れ霜」って何よ。と、引っかかってしまいました。
「八十八夜」とは、唱歌の「茶摘み」でおなじみの、「夏も近づく八十八夜」の八十八夜のことです。立春を起算日にして88日目、だいたい5月2日頃です。この日ぐらいまでは遅霜が降りることがあり、農家の方は霜の対策をしないといけないのですが、逆に、この頃を境に気候が良くなり、そろそろ霜の対策をはずしても良い。霜とはさようなら。ということで、「別れ霜」なんだそうです。昔の人は粋な言葉を考えますね。
ということで、「霜とお別れ」と「恋人とお別れ」を引っ掛けて、5月13日が「別れの日」だそうです。
ところで、バレンタイデーから88日目が5月13日頃なんですが、「八十八夜」は立春の日を含めて88日目、「別れの日」はバレンタイデーの翌日から88日目、バレンタインデーを含めると89日目にあたります。数え方がおかしい。「別れの日」を決めた方が数え方を間違えただけなのか、なるべく5月14日に近づけたかったのか、真相はどうなんでしょうか。
と、くだらないことが気になった水西でした。
祝!合格!
2013.03.21 | カテゴリ:スタッフブログ
もう3月も20日を過ぎましたね。
ようやくうちのお兄ちゃんの受験が終わり、月曜日に発表がありました。
朝、10時からの発表に私も一緒に高校まででむき、15分前からスタンバイ
5分前に先生が合格者の番号を書いたボードを半分にたたみ、スタンバイ
私も息子も緊張感が半端なく無言で手を合わせるのみ そしてとうとう10時・・・
そしてとうとう10時・・・
ありました~
![]() 「 3122 」
「 3122 」 何度も間違いないか見直しました! 間違いなく、ありました~
何度も間違いないか見直しました! 間違いなく、ありました~![]()
息子は少しうっとうしそうでしたが、思わず抱きついていました
ほんとにおめでとう! よく頑張りました
今まで一生懸命、公文に塾にがんばって、第一志望の高校に春から通える事になりました
楽しい高校生活を送ってね。 母より
植田でした。
ホワイトデー
2013.03.17 | カテゴリ:スタッフブログ
こんにちは!花粉なのか風邪なのかPM2.5の影響なのか解りませんが、
鼻水に苦しんでいる中尾です(+o+)
みなさんは大丈夫ですか?
さて、今回は3月14日の「ホワイトデ-」について調べてみました。
私も娘や会社の同僚にいただきましたので、「ベルギー王室の御用達」の「ゴディバ」をお返ししましたが、
・ホワイトデーは、一般的にバレンタインデーにチョコレート等を貰った男性が、そのお返しとしてキャンデー・マシュマロ・ホワイトチョコレート等のプレゼントを女性へ贈る日。日付は3月14日。この習慣は日本で生まれ、中国・台湾・韓国など一部の東アジアでも定着している、欧米ではこういった習慣は見られない。・
との事でした。
なんと日本が作った習慣だったのですね!!
あと、関連する日としては
- ●バレンタインデー
- ●オレンジデー(4月14日)
- オレンジやオレンジ色のプレゼントを贈る日。
- ●ブラックデー(韓国、4月14日)
- バレンタインやホワイトデーに縁の無かった男女が黒い物を飲食する日。
- ●メイストームデー(5月13日)
- 別れ話を切り出すのに最適な日、別れ話を切り出していい日。
- 「八十八夜の別れ霜」に由来。
と、いろいろな日があるものですね。
今回の「ホワイトデー」では、全国でどれだけの「カップル」が生まれたのでしょうか?
私たちの扱っている「保険」も各社いろいろな商品がありますが、どれに入るかよりも、
各自、自分に合った保険に入いるかが重要です。
保険に迷ったら・・・
当社は「ファイナンシャルプランナー」はじめ、いろいろな有資格者がおり、
「あなただけの、あなたにピッタリの保険」をお勧めします。
2月14日や3月14日だけではなく、毎日、受け付けておりますので、
「保険に迷ったら?」「保険とは?」「どんな保険があるの?」
保険の事なら迷わず「シーエフ」へ
お待ちしております。(●^o^●)
スマホ襲来!?
2013.03.10 | カテゴリ:スタッフブログ
我が家にも遅ればせながらスマホがやってきました。といっても私が持ったわけではなく、ランニングコストの関係でまずは子供たちから。ということで、2台がスマホになりました。
二人は、もっぱらゲームで楽しんでます。ガラケーの時にはネットにはつながせなかったので、ケイタイゲームではなくDSなんかを持たせてました。新しいゲームで遊べるからですかねぇ、ここ数日はDSはほったらかしで、もっぱらスマホで遊んでいます。母親がキレなければいいですが。
さて、シーエフのスマホ状況はというと、営業で持ってないのは私だけなんです。(クラークにも一人ガラケーユーザーいまして、二人でなんとなく肩身の狭いお思いをしてます。)
専務は、仕事上でで有効にスマホを使う計画があるようで、「早くスマホを持つように」と、やいやい言っております。
便利なんでしょうねぇ~。早く持ちたいなぁ~。などと、こどものようなことを言っている水西でした。
ひな祭り
2013.03.03 | カテゴリ:スタッフブログ
こんにちは(●^o^●) 2月は「逃げる」でバタバタし通しだった中尾です。
3月は「去る」で逃げられない様に、日々頑張りたいと思います。
さて、3月と言えば「ひな祭り」ですが、我が家にも長女と長犬?がいるので、みんなで
ケーキ&ちらし寿司を食べました。
なぜ「ひな祭り」の日は「ちらし寿司」なのか?疑問に思い、早速調べてみました。
ひな祭りの由来
もともと「ひな」というのは、女子が人形遊びなどに使ったもので、平安時代には立ちびなだったものが、室町以降座りびなとなり、今のようなひな人形が作られるようになったのは近世中期以後。
「桃の節句」はもともと春先に農作業をはじめるにあたり、物忌み、禊などを行い穢れを払う行事であり、人形はもともとこの汚れをうつして川などに流す「形代」として使用されていたらしい。従って、特に女子の祭りというわけではなく、男女が共に参加した。
一方、「端午の節句」はもともと田植えを前に稲作の吉凶を占う行事であり、そのため、田の神(女性)との関わりが深かったらしい。二つの行事が今のように男子・女子の祭りとして認識され、華美になってきたのは、ごく最近の近世中期以降だという。
ひな祭りの食事
ちらし寿司
ちらし寿司の具のエビは「長生き」、レンコンは「見通しがきく」、豆は「健康でまめに働ける」とされる。
縁起もののハマグリや、サザエなどの巻貝
貝類はペアになっていることから、良縁の象徴。
ひし餅
ひし餅の三色は、赤は「桃」白は「雪」緑は「草」を表しており、3月という季節の情緒を表現している。
ひなあられ
野外でひな遊びを楽しむときに持って行くための携帯食料が由来。 だそうです。
誰でも知ってる「ひな祭り」と言う言葉ですが、由来など全然知りませんでした・・・(+o+)
日本人に生まれたからには、「四季折々の行事」等に関心を持ち、ゆっくり楽しみたいと
思う今日このごろです。
みなさんも日々、忙しい時間をお過ごしだと思いますが、たまにはゆっくりして下さいね(●^o^●)